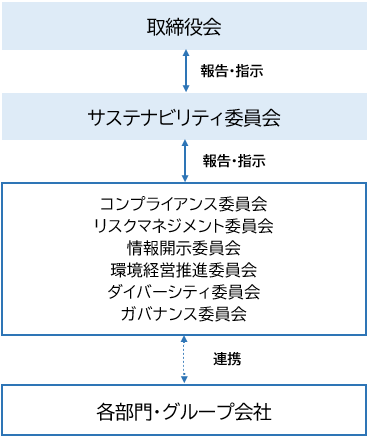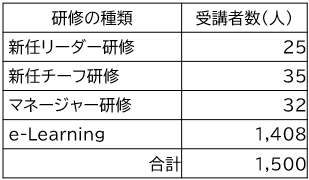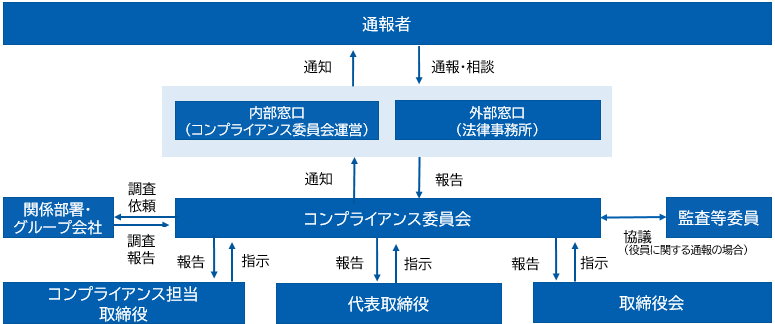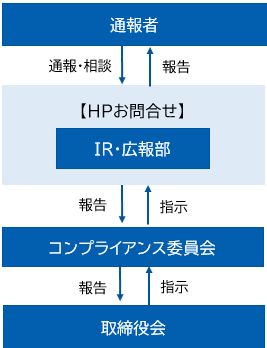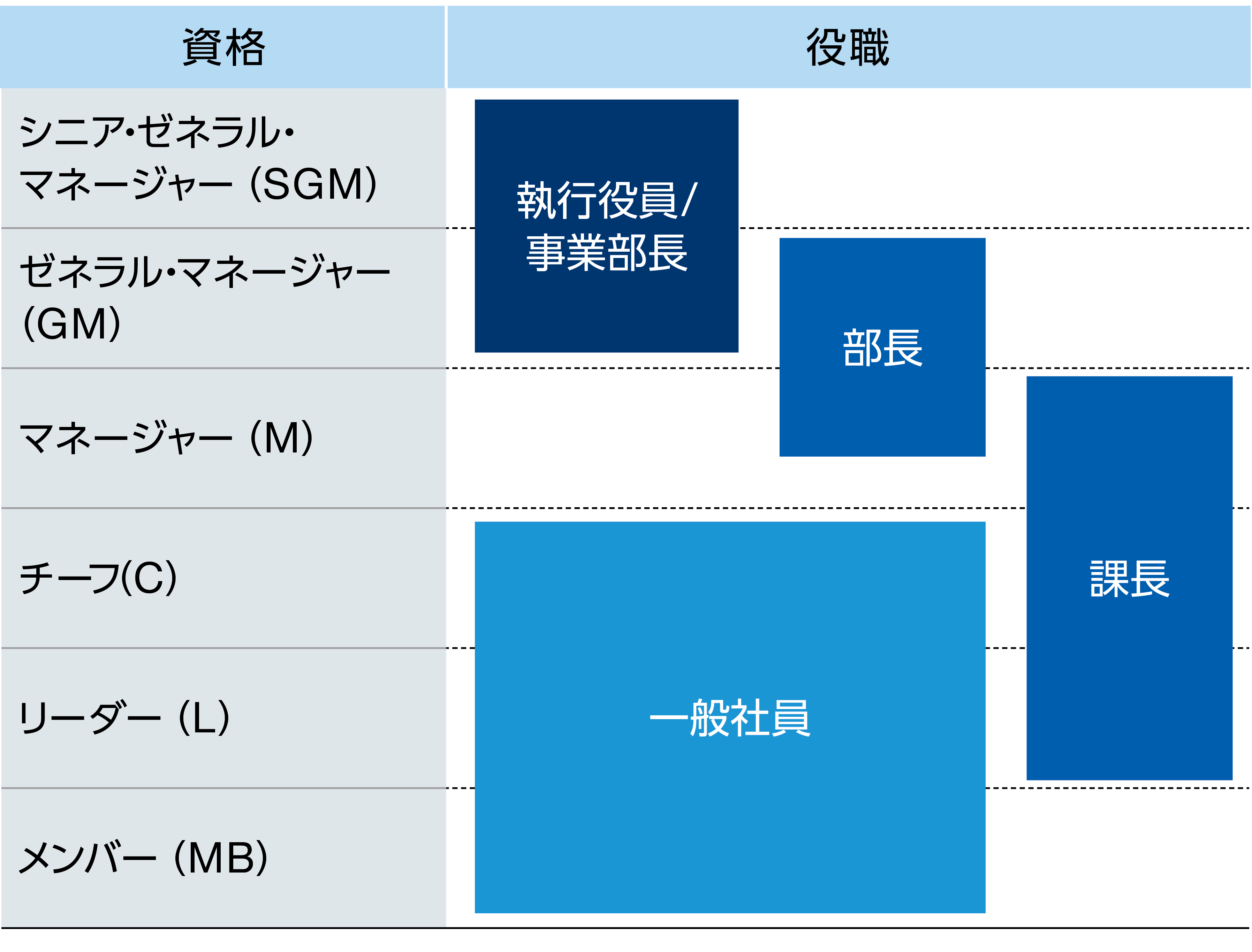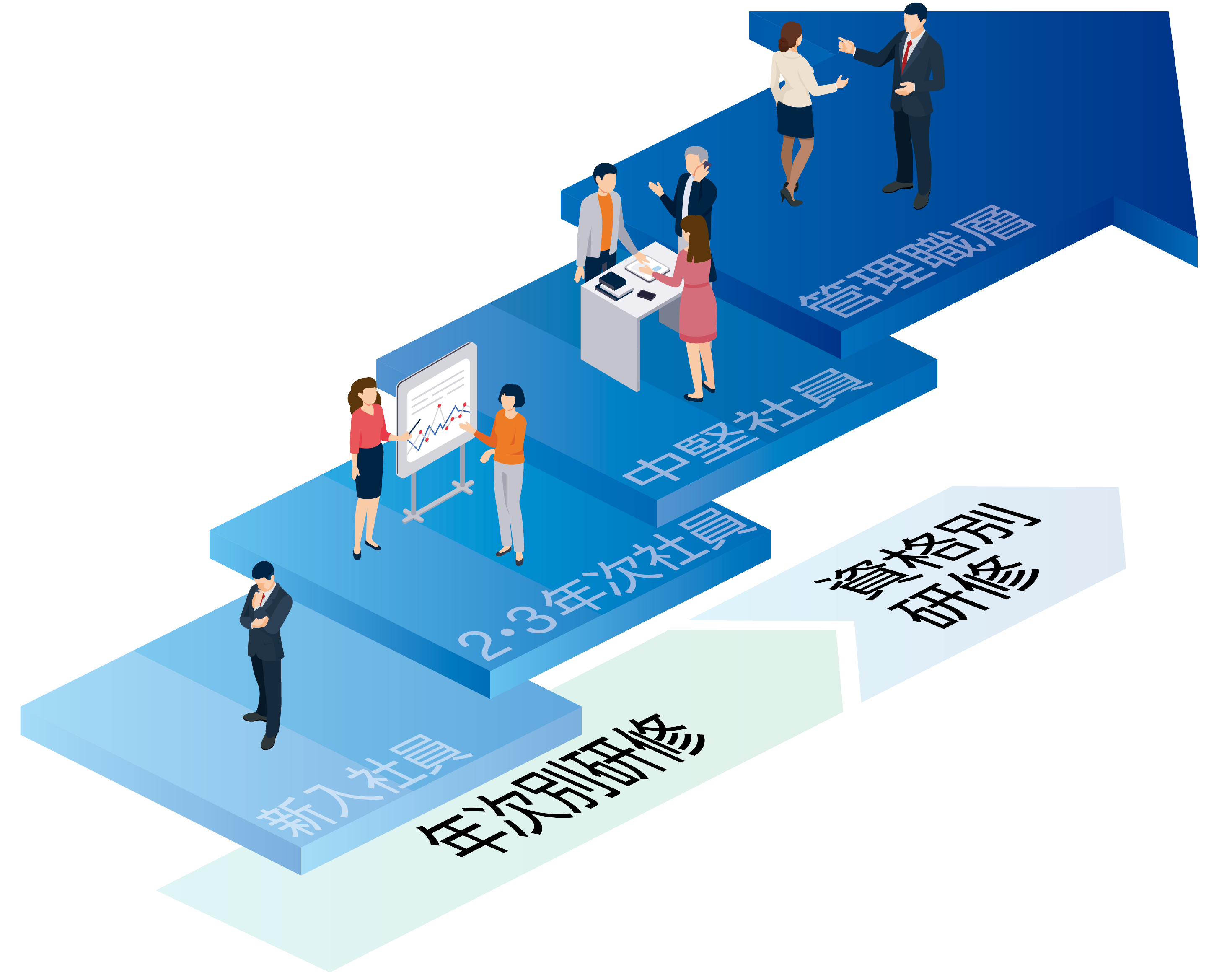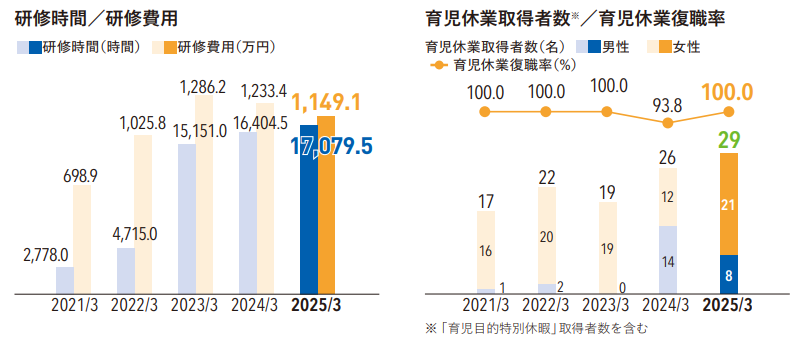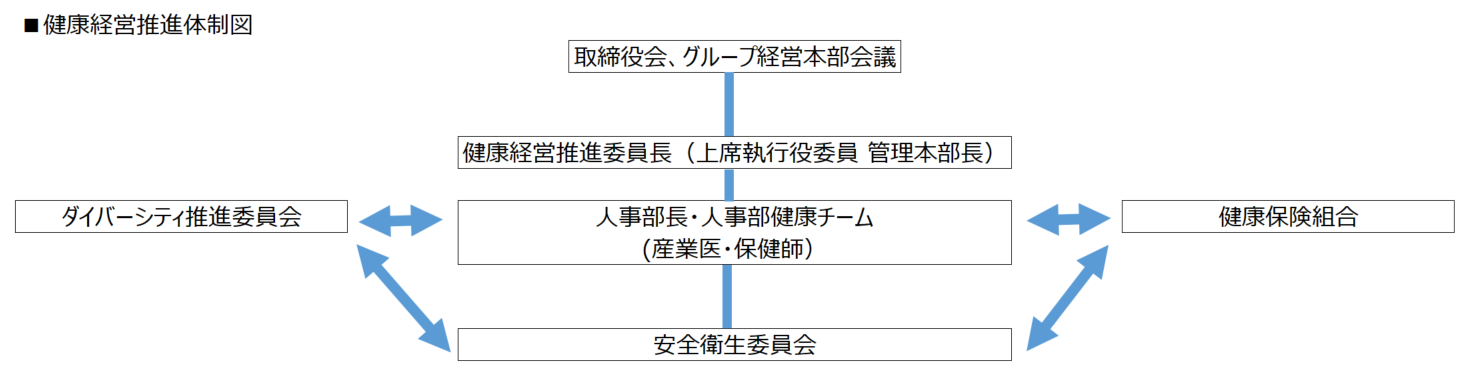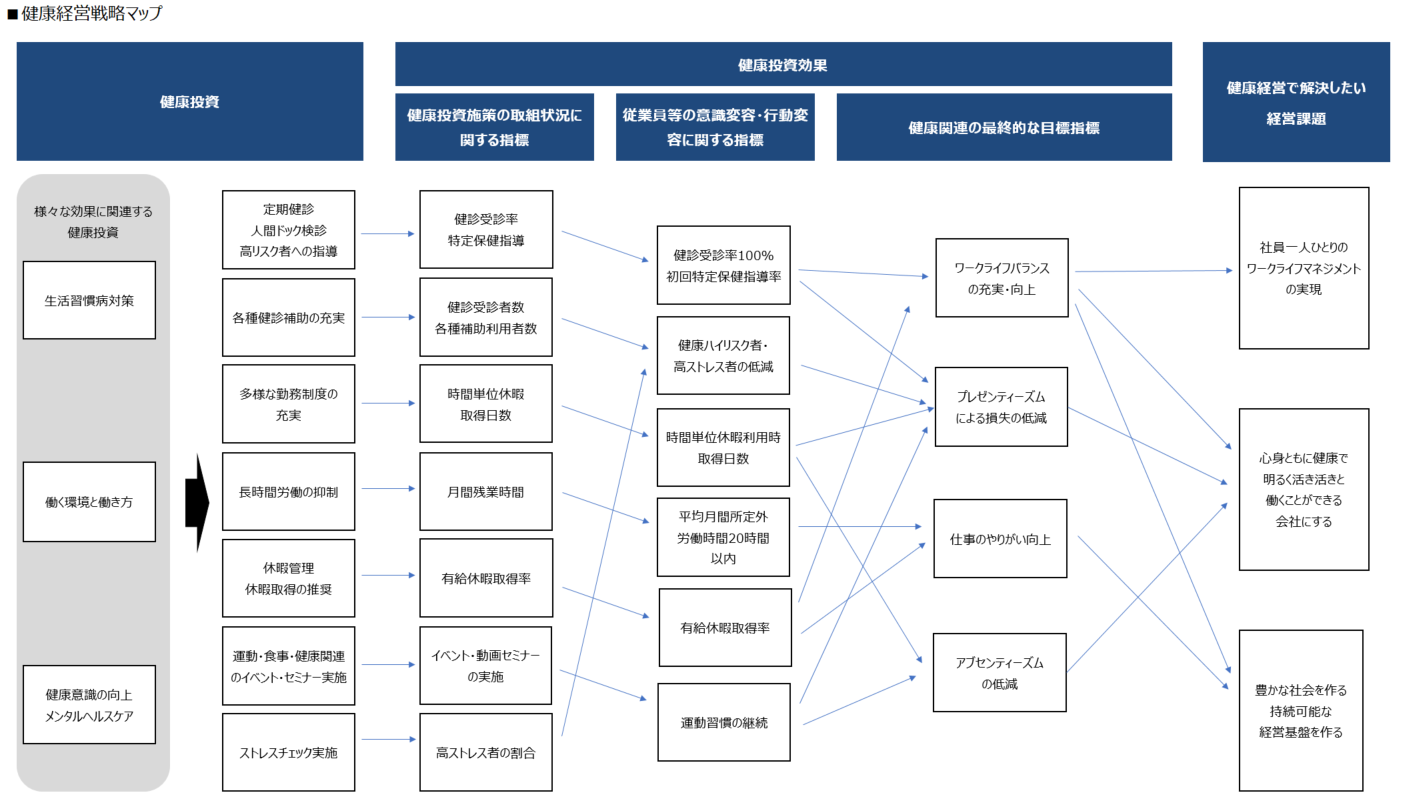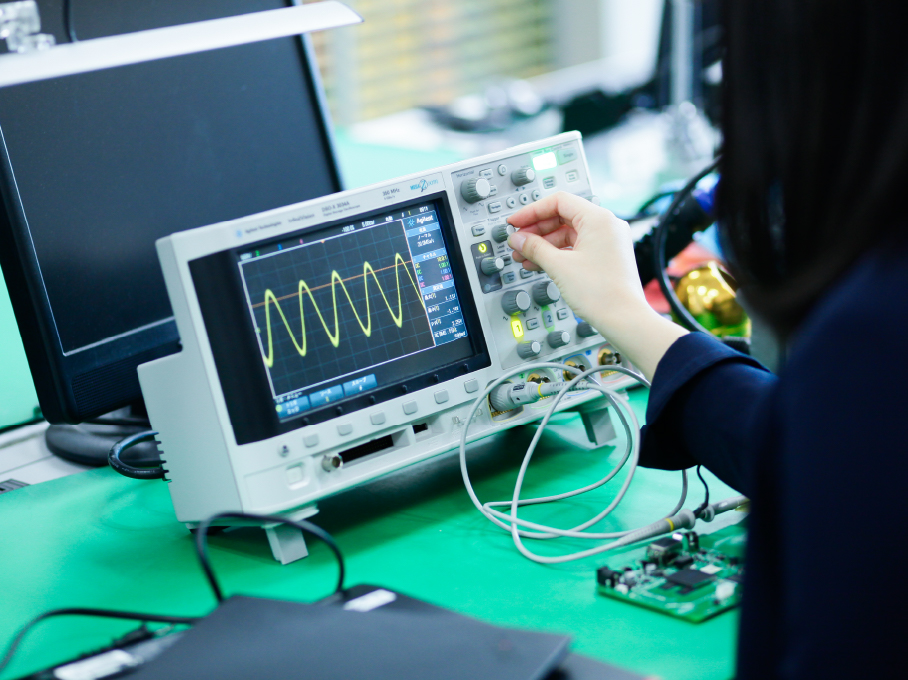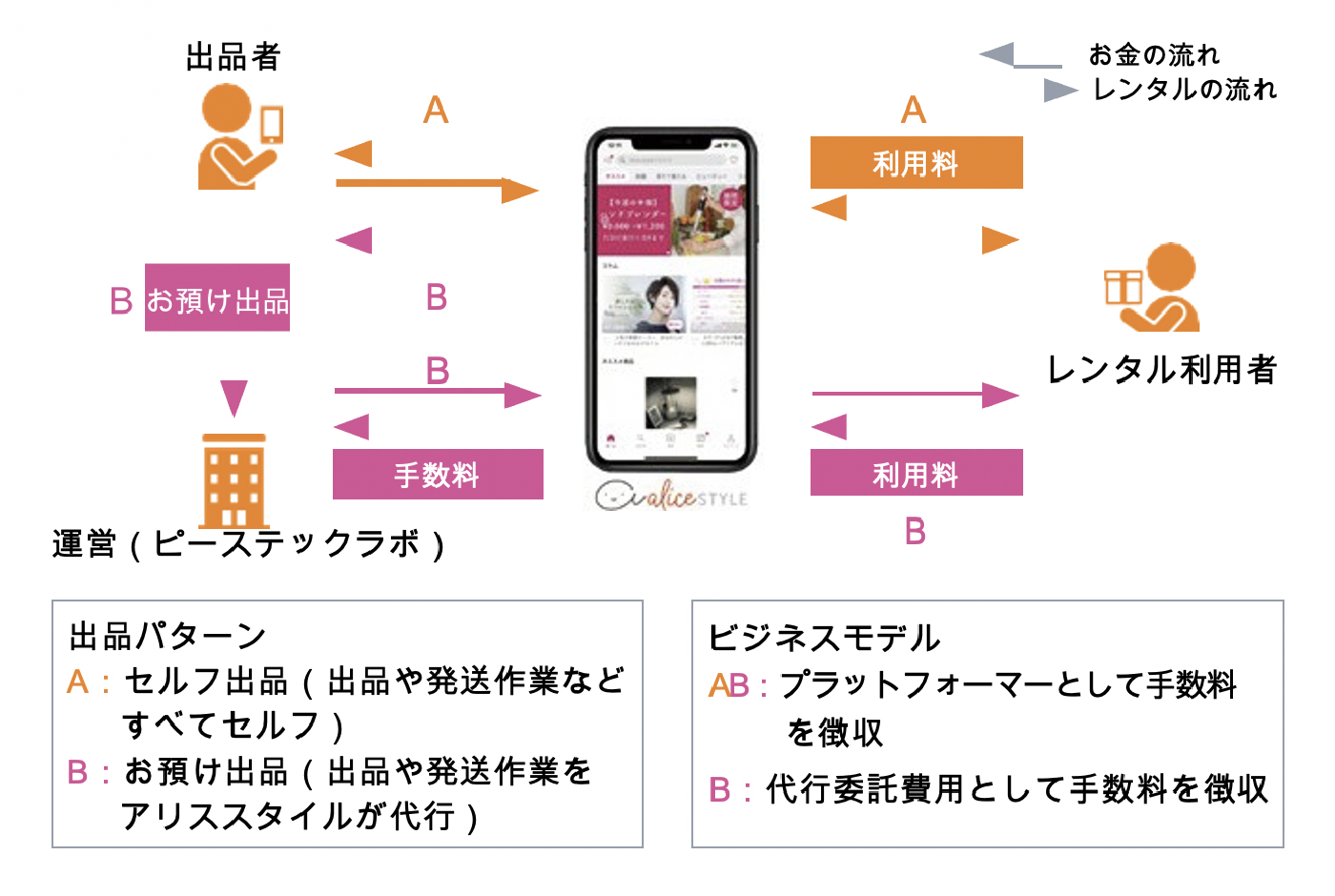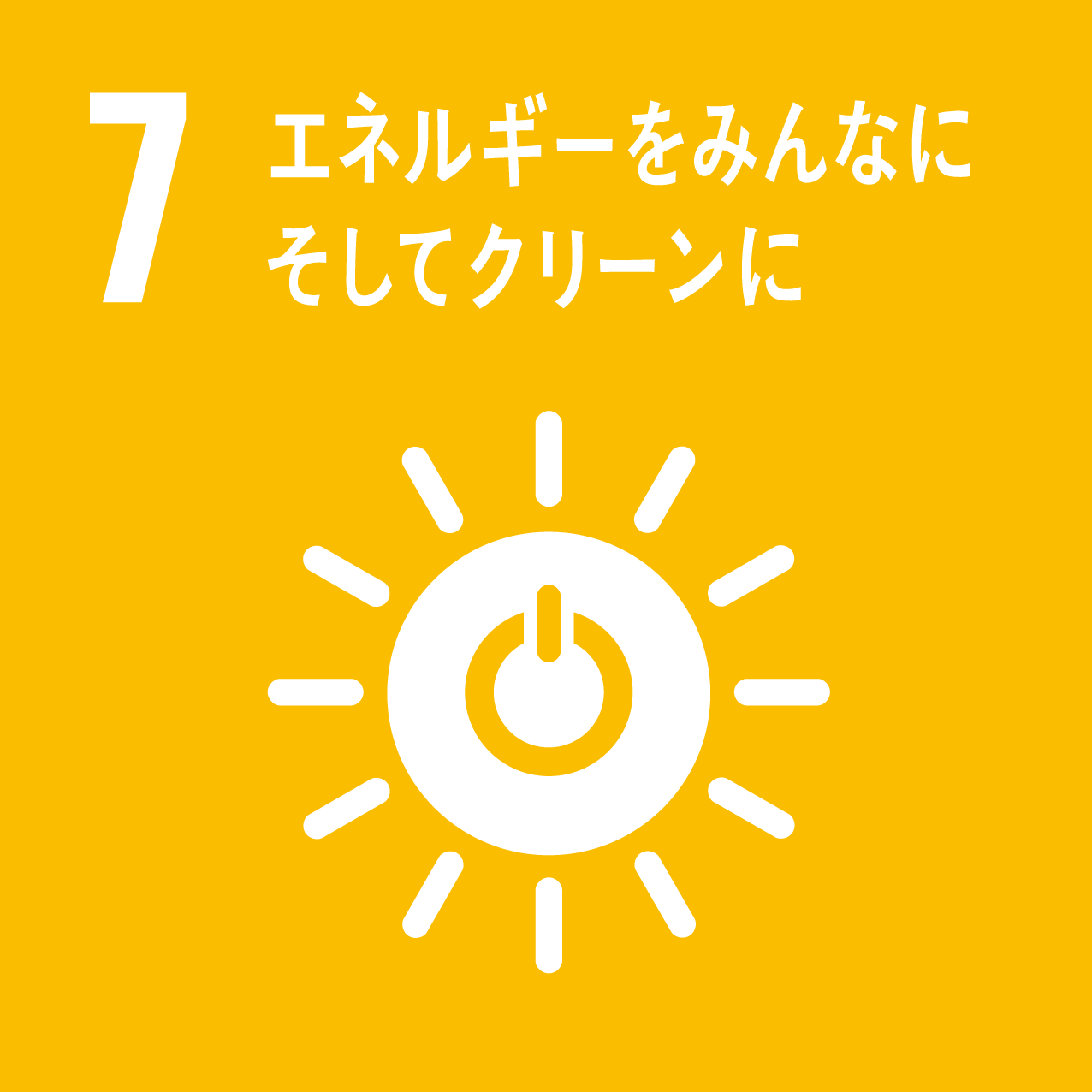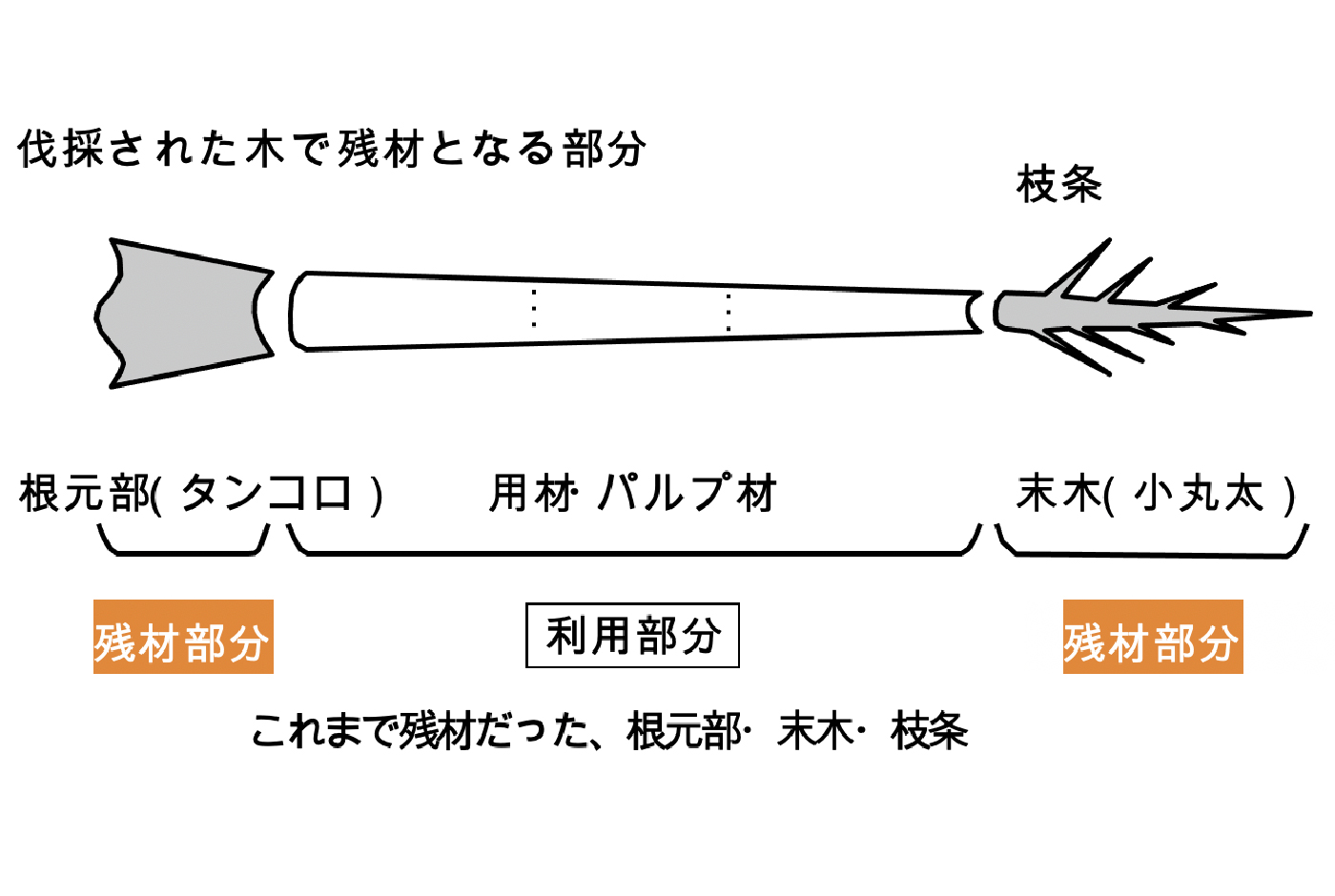国際規範の支持・尊重
加賀電子グループは、「国際人権章典」や「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」など、人権に関する国際規範を支持します。また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権を尊重してまいります。
人権デューデリジェンス
加賀電子グループは、人権尊重のため人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、その仕組みを通じて、事業活動による実質的、または潜在的な人権への負の影響を特定し、それらに対処することで、防止・軽減に努めます。
救済と是正
加賀電子グループの事業活動において、人権に対する負の影響を引き起こした、あるいは関与が明らかになった場合には、適切な手続き・対話を通じてその救済と是正に取り組みます。
対話・協議
加賀電子グループは、取引先や株主・地域社会の方々など、関係するステークホルダーの皆様との対話と協議を通じ、当社グループの事業活動が与える影響の可能性について相互理解を深めることで、事業、商品やサービスの改善につなげるとともに、人権尊重の取り組み向上と改善に努め、社会への貢献と共生を目指します。
啓蒙・教育
加賀電子グループは、本方針が全ての事業活動に適切に組み込まれ実行されるよう、全ての役員および社員(契約社員、派遣社員などを含む。以下同じ)に対して必要な啓蒙・教育を行います。
情報開示
加賀電子グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて継続的にモニタリングし、その進捗状況と結果をウェブサイト等を通じて開示し、透明性の確保に努めます。
適用範囲
本方針は、加賀電子グループの全ての役員および社員に対し、適用されます。また、当社グループは、事業活動におけるビジネスパートナーやその他の関係者に対して、本方針を遵守し人権を尊重することを期待します。